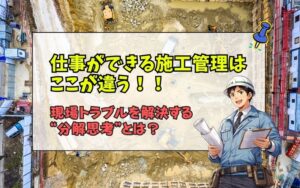時代の変化に伴って、働き方が変わってきているのは皆さんもご存じでしょう。
今日は、働き方のひとつである【ジョブ型雇用】についてお話していきます。
人手不足が課題となっている建設業界にとっては、解決策にもなり得る「ジョブ型雇用」を、より生かすために正しい育成方法を知っておいて欲しいと思います。
今後の建設業界をより良くしていきたいと考えている方に是非およみいただきたいです。

株式会社 RaisePLAN 代表取締役
武田 祐樹(たけだ ひろき)
【これまでの活動】
- 総合建設業に17年在職後、独立起業。
- 建設現場の生産性向上支援や施工管理の教育支援を展開。
- 中小企業デジタル化応援隊事業(中小企業庁)のIT専門家。
- YouTubeや音声配信、Instagramなどで情報発信を行い、電子書籍の出版やオンライン講師、オンラインセミナー活動に積極的に取り組む。
- 建設業の現場効率化の仕掛け人としてAbemaPrimeに出演(2023年3月)。
「ジョブ型」とは?

今までのように、様々な職務に対応する働き方ではなく、特定のスキルのみを深く掘り下げて、それで勝負するという働き方をする人を「ジョブ型社員」といいます。
また、職務内容を明確に提示し、その職務を全うするのにふさわしいスキルがある人を採用することを「ジョブ型雇用」といいます。
建設業界での「ジョブ型社員」の具体的な例としては、「施工図屋」というものがあります。これは、各所の施工図、各現場の施工図を一手に引き受け、図面をかくことにおいてプロフェッショナルな人材を指します。
こうすることのメリットとしては、現場で職人との直接的なやりとりが苦手な人でも、得意分野を生かして建設業をサポートし、現場運営に貢献することができることです。
従来のような職種や職務内容を限定せずに採用をし、会社の業務命令のもとで職務をローテーションするという働き方と比べると、「ジョブ型雇用」はとても効率的といえます。
必要を感じて、「ジョブ型雇用」を導入したのであれば、その本質を理解し、専門スキルをみがくことに専念できる環境を整えることが大切です。
「ジョブ型社員」教育
「ジョブ型雇用」の新卒者に対する教育に悩む方も多いでしょう。
ここからは「施工図をかくこと」に専念した「施工図屋」を例に挙げ、「ジョブ型社員」をどのような手順で育成していくのがよいのかという点についてお話していきます。
目指すべき姿を考えよう

「ジョブ型雇用」をされた社員に対して、会社が望んでいることは何でしょうか。
「ジョブ型社員」に望むことは、多様な業務をこなすことができるようになることではなく、とにかく特定の業務を効率よくこなすことではないでしょうか。
つまり、「施工図屋」の場合に望まれていることは「とにかく施工図をかく」ということです。
施工図をかくための知識さえあれば業務に支障はないといっても過言ではありません。
これを踏まえて、「ジョブ型雇用」された新入社員に対してどのようにアプローチをしていくとよいのか考えていきましょう。
アプローチする狙いを定めよう

建設業界の教育方法として、とりあえず数年現場に出てみろという考えがあります。
もちろん、現場に出ることで、実際の作業の流れを理解できたり、現場の雰囲気を知ったりすることができます。
しかし、「施工図屋」つまり、施工図をかくというスキルに特化した「ジョブ型社員」を育てたいということに焦点を当ててみると、とりあえず現場にでる必要はないのでないかという見解が見えてくるのです。
「施工図をかく」という業務は、現場を見たことがなくてもやり遂げることができるのです。
むしろ、現場のあれこれを知らないからこそ、「施工図をかく」ということに集中できるのではないでしょうか。
職人さんの気持ちや元受け側の気持ちが分かってしまうと、情を含め、あれこれ考えることとなり、「施工図をかくこと」に対しては弊害となってしまうことが多いと思います。
よって、私の考えは、最初に必要なテクニックを学び、専門的なスキルに集中することができる環境で、数年かけて、ある程度腕を磨いでから、その後、現場の現状を学ぶ方が効果的だと思います。
まとめ

ここまで「ジョブ型社員」の育成方法についてお話してきました。
専門的なスキルに特化した人材を雇うからには、プロフェッショナルとして最大のパフォーマンスができるように教育できると良いと思います。
たくさんのことを考えながら進めるという一般的な考えを捨て、先に専門的なスキルの基本をしっかりと習得し、それから応用を学ぶ方が「ジョブ型社員」としての成長は早く、現場の具体的な状況を反映しやすくなると考えます。
つまり、施工図のプロフェッショナルを目指すなら、このアプローチが最終目標に到達するのに最適だと思います。
教育をする際には、その社員に求めるものは何か、ゴールはどこに据えるのかという部分を念頭において、その社員にとって一番成長が早い方法を選択していくべきだと思います。